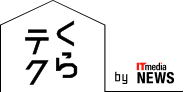マイナス20度、エクストリームな冬山で「EXILIM G EX-G1」を試す:レビュー
ツールナイフのような武骨さえ漂わせる「男子カメラ」が、カシオ計算機の「EXILIM G EX-G1」だ。そのデザインを裏切らない、耐水・耐衝撃・防じん性能・耐低温というタフネス性能を兼ね備えており、「過酷な環境下で、過激なアクションをいかに臨場感をもって記録するか」をテーマに開発されたということだけはある。
そのEX-G1を真冬の八ヶ岳へ持ち込んだ。過酷な環境下での使用感をお伝えする。
八ヶ岳は標高2899メートルの赤岳を最高峰とする山塊の総称で、四季折々の表情で訪れる者を楽しませてくれるが、あいにく当日は外気温マイナス20度、稜線(りょうせん)にでる前から風速15メートルというかつて経験したほどがないほどの悪条件だった。
しかし、これほどの極低温環境でもEX-G1は平然と動作した。EX-G1はIPX8およびIPX6相当の「防水性能」とIP6X相当の「防じん性能」、2.13メートルからの落下に耐える「耐衝撃性能」、マイナス10度の低温環境下利用に耐える「耐低温性性能」と、4つのタフネス性能を兼ね備えるのだが、これは今回のような環境下で、撮影時に心理的なハードルを大きく引き下げてくれる。寒かろうが、雨が降ろうが、お構いなしでシャッターを切れるからだ。
今回の環境であるマイナス20度というのは、明らかにスペックの限界を超えているが、動作に鈍さを感じることもなく、バッテリーの保ちも良好。バッテリー容量は700mAhと手持ちのニッケル水素充電池とほぼ同容量だが、フラッシュを使わないでいれば1日フルに使えるだろう。同時に持ち込んだ、ニッケル水素充電池を利用する照明器具が寒さで電圧を低下させる中、このカメラは元気に動き続けてくれた。
休息で立ち寄った山小屋でも使い続けたが、外気との温度差が20度以上ある状態でも内部に結露が発生しなかったのは見事。さすがに外側には若干の結露がみられたが、内部は一切結露なし。シーリングの強固さを垣間見た。
今回のような極低温の冬山へ持ち込む場合、実は結露が溶けるなどを除けば、「カメラが濡れる」シチュエーションはあまりない。外にいる限り雪は溶けないからだ。しかし、テント場へついた際、気温低下と体から発せられる湿気の結露によって、ものの見事にカメラは凍り付いていた(なにせマイナス20度だ)。それでも、電源を入れると問題なく起動し、レンズをグローブでぬぐえば通常通りの撮影が行えた。
実はコレ、かなりスゴイことなのだ。カメラ内部が結露してしまった状態で外に出ると、場合によってはその結露が凍り付いてしまうことがあり、それ以後の撮影ができなくなってしまう恐れがある。極低温下にカメラを持ち込む際に、最も気をつけなくてはならないことのひとつがこの内部の結露なのだ(同時に持ち込んだデジタル一眼レフはものの見事にこの状態となってしまった……)。
ボタンのサイズから、厚手のウィンターグローブをはめていては操作がしにくいかもと思っていたが、意外なほどスムーズに操作できた。これは筆者がグローブをはめた状態での撮影になれているせいもあるだろうが、ボタンに適切なクリック感があり、それはグローブ越しにも伝わってくる。

 あまりの悪天候に登山をあきらめふもとでアイスクライミング。クライミング中は上から氷が思いっきり降ってくるので、カメラを破壊しかねない環境なわけだが、このカメラに至っては無造作にその辺にほったらかしにできる。行動をスポイルしないカメラの真骨頂
あまりの悪天候に登山をあきらめふもとでアイスクライミング。クライミング中は上から氷が思いっきり降ってくるので、カメラを破壊しかねない環境なわけだが、このカメラに至っては無造作にその辺にほったらかしにできる。行動をスポイルしないカメラの真骨頂携帯時のポイントは、チェストベルトをネックストラップの下に通すこと。ちょっとしたことだが、操作の自由度が違う。オプションのネックストラップは適切な長さで、これも好印象。ARTISAN & ARTISTのように素材に厚みがないのはさみしく感じるが、折りたたむとカメラごと胸ポケットへ収納できるメリットがある。
これからの時期ならば、沢登りをする人(シャワークライマー)やラフティングのおともにもおすすめしたい。薄くて軽いので、ヘルメット用アタッチメントなんかもあるとうれしい。どうしてもアウトドアでの利用ばかりに目が行きがちだが、「手荒に扱っても構わない」カメラは小さな子どもがいても壊される危険性がないうえ、撮影領域を拡大してくれる。川辺でのバーベキューに持ち込んだりしても楽しいだろう。
後日、EX-G1をクライミングジムへも持ち込んだが、床に置きっぱなしにして登っているシーンを撮ったり、わりと危ない動きがあるシーンを寄って撮りに行ったり、滑り止めチョークにまみれた手でいりじまわしたりと、本製品のタフネスさは本当に頼りになると実感している。
関連記事
 永山昌克インタビュー連載:大都会にも大自然にも似合う“男のカメラ”――「EXILIM G EX-G1」開発者に聞く
永山昌克インタビュー連載:大都会にも大自然にも似合う“男のカメラ”――「EXILIM G EX-G1」開発者に聞く
女子向けカメラはもうたくさん。男子にこそ使って欲しい、と開発者が語るのはカシオの耐衝撃デジカメ「EXILIM G EX-G1」。G-SHOCKに通じる堅牢性と、アシンメトリーな個性派デザインが光るカメラだ。 写真で見る、タフネスデジカメ“EXILIM G”「EX-G1」
写真で見る、タフネスデジカメ“EXILIM G”「EX-G1」
カシオ計算機のデジタルカメラ“EXILIM G”「EX-G1」を写真で紹介する。腕時計「G-SHOCK」を連想させるスポーティーなフォルムに注目だ。 Enduranceするすべての人へ贈るEXILIM G「EX-G1」、発進
Enduranceするすべての人へ贈るEXILIM G「EX-G1」、発進
スポーティーなフォルムとタフネス性能を兼ね備えたデジタルカメラ“EXILIM G”「EX-G1」が販売開始される。Enduranceするすべての人へ贈る製品だ。 カシオ、薄型タフネスデジカメ“EXILIM G”「EX-G1」
カシオ、薄型タフネスデジカメ“EXILIM G”「EX-G1」
腕時計「G-SHOCK」を連想させるスポーティーなフォルムとタフネス性能を兼ね備えたデジタルカメラ“EXILIM G”「EX-G1」がカシオ計算機から登場。
関連リンク
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR