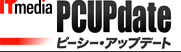 |
| |||||||||||||||||||||
製品情報FEED BACK最新の記事
|
日本のホスティング・マーケットの歴史と現状を探る(1/1)前回ハイパーボックスの変遷とその根底にある文化について聞いた。だが実際にホスティング業界はどのような歴史と変遷を歩んできたのだろうか。歴史を紐解きつつ、昨今のホスティングサービスの是非について考えてみたい。インターネットの黎明
当時はまだインターネットよりはパソコン通信がよく利用されていた。大分の官民が協力して設立されたコアラネット(現在のニューコアラ)がサーバの24時間運転を開始したのが1985年9月。NIFTY-Serveがサービスを開始したのが1987年4月だ。1990年にはリンククラブが活動を開始。同年にハイパーネットが創業する。 これらサーバに電話回線を通じてアクセスするパソコン通信は、次第にインターネット接続サービスへと発展を遂げてゆくのだが、それはまだ先の話だ。当時は現在の掲示板のような“会議室”にて発言し、そのログをダウンロードしてゆっくりと読むといったことを行っていた。通信回線速度が28800kbpsになるのは90年代後半の話で、当初は300/bps程度であった。 パソコン通信にはメールアドレスというものはなく、サービスを提供する会社から支給される固有ID番号が自分のものになる、という形態であった。ファイルを保管するサービスなども存在したが、いかんせん回線と通信速度は当時はいかんともしがたい状況であった。 1991年、米国でWWWサービスが開始され、日本でもDNSの運用が開始される。そして1992年、JNIC(JPNICの前身)が日本におけるIPアドレス割り当てと管理を開始する。ちなみに1992年、NTT移動通信企画株式会社がNTT移動通信網株式会社に改称している。 そして1993年、米国でhtmlブラウザMosaicが開発され、InterNICが活動を開始。同年日本でもJPNICが発足し、日本でのIPアドレス逆引きをJPNICがInterNICから引き継いでいる。インターネット時代がようやく近づいてきたわけだ。 インターネットに“繋がる”時代
1994年、米国でhtmlファイルを閲覧するソフトNetscapeが、Mosaic開発者によって開発される。今日のWWW文化はこのブラウザから始まったと言っていい。同年、ニフティがインターネット接続サービスを開始。NETWORLD+INTERROP JAPANが開催され、INTERNET Magazineが創刊した年でもある。 1995年、米国でYahoo!がサービスを開始する。あっという間に普及しつつあったホームページの中から、いかに目的の情報にたどり着くか。検索エンジンサービスが必要とされるほど、インターネットは爆発しつつあったのだ。日本でも同年、インターキューが世界初の非会員制インターネット接続サービスを開始する。 当時日本では、ダイヤルQ2と呼ばれた、電話をかける人がサービス料を支払う形態の電話サービスが繁栄しており、その仕組みをそのままインターネット接続サービスに置き換えてサービスを開始したのが、インターキューである。翌年にはSo-netもサービスを開始した。 当時はインターネットに接続する、ということが第一義であった。インターネットに繋がれば世界中の人とメールをやりとりでき、ホームページを閲覧できる。インターネットで世界が変わる、そんなことが自然に想像できた、牧歌的な時代でもあった。だが、単に情報交換をするだけでは人間は満足できなくなる。通常の社会規範では許容されないさらに深い情報を、そして金銭を伴いつつ。 ネットには繋がった、次は……
単純なインターネット接続サービスの次にやってくるのが、さらなる高次元のインターネットサービスだ。現在「ホスティング」「レンタルサーバ」などと呼ばれるサービスであり、本特集で語られるとおり、いまだ発展途上の大開拓時代いるとも言える業界だ。 1996年、この年ハイパーネットがHot Cafeサービスを開始する。これはWebページと広告を別ウインドウにして表示するというアイデア。ネットベンチャーの草分けとして名をはせたハイパーネットは、インターネットバブル期前に破産し、さまざまな話題を提供することになる。 この年、日本で事業を行っているホスティング業者の主だったところが事業を開始している。アイル、ファーストサーバ、そしてハイパーボックスだ。なかでもアイルは、ホスティング専業の業者として初めてJPNIC会員になるなど、その社会的存在が次第に現れてきた。 1997年はJPNICが社団法人化し、So-netがポストペットを発売し、Yahoo! JAPANが店頭公開した年であり、ハイパーネットが破産申請した年でもある。アイルは米国子会社を設立した。1998年には、光通信までもがレンタルサーバ事業を開始している。 今日インターネットといえば、いまだ多くの人にとってはWebページ閲覧とメールサービスだ。だが、インターネットに付随するサービスは、コンシューマーおよびビジネスの世界で、多様に発展を遂げている。 WWWサービス、DNSサービス、メールアドレス発行サービス、掲示板、チャット、brog、などといったもののほか、データストレージサービス、データベース構築など、お金を出せばいかような規模でも、要望に応じてカスタマイズされたインターネットサービスを買うことができるようになった。 こうした現代的なサービスは、この時期より発展を始めたのだ。そしてそのサービスは、後にインターネットバブルと呼ばれる時代に広く一般に浸透することになる。 関連リンク [飯島俄,ITmedia] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



|
||||
ITmediaはアイティメディア株式会社の登録商標です。


 ここでまず、日本におけるインターネットの歴史を、おさらいしていこう。1984年、米国でのインターネット開始とともに日本でもJUNETが開始された。翌年1985年4月には電気通信事業法が施行され、日本電信電話公社(NTT)が民営化。電気通信の分野における自由化が始まった。
ここでまず、日本におけるインターネットの歴史を、おさらいしていこう。1984年、米国でのインターネット開始とともに日本でもJUNETが開始された。翌年1985年4月には電気通信事業法が施行され、日本電信電話公社(NTT)が民営化。電気通信の分野における自由化が始まった。