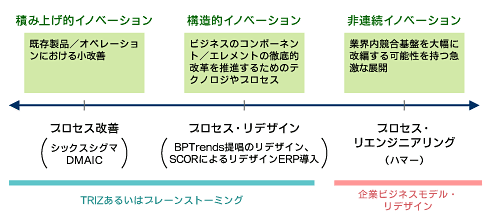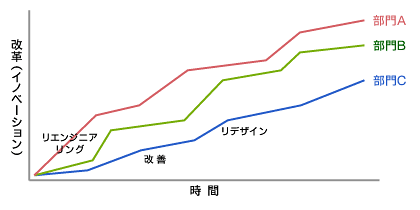ビジネスプロセス改革と3つのイノベーション:BPTrends(9)(2/2 ページ)
プロセスイノベーション連続体仮説
現実を直視しよう。ほとんどあらゆる人が、新しいアイデア、新しいメソッド、および新しいデバイスの導入に取り組んでいるのが現実だ。ある物事は他の物事より新しい。このことに疑いはない。そして、誰もが、物事の新しいやり方を求めているのだ。
いうまでもなく、イノベーションを適切に理解するには、それを連続体(※訳注)として把握しなければならない。筆者がこれまでに目にした中では、チャールズ・A・オライリー(Charles A. O'Reilly III)とマイケル・L・タッシュマン(Michael L. Tushman)による論稿が、この連続体に関する資料として最も優れている。前述と同じHBR 2004年4月号に掲載された、「The Ambidextrous Organization」(※4)と題する記事である。オライリーとタッシュマンは多数のイノベーション事例について精査した結果、下図のような連続体の概念を提示した。
【参考リンク】
※4 邦訳:既存事業と新規事業の並立を目指す 「双面型」組織の構築(DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー 2004年12月号)
※訳注:連続体=生態学における概念。植生群集は多種の個体群の重なりによって成立し、環境傾度に沿って連続的に移行すること
図1 オライリーとタッシュマンのイノベーション連続体
矢印の上の部分は、オライリーとタッシュマンが、研究対象としたさまざまのイノベーション事例を位置付けるのに用いる3つのカテゴリを示す。矢印の下は、筆者が付け加えたプロセス改革の3つの一般的アプローチである。さらにその下には、最もよく知られた3つのイノベーション手法が適用されるであろう領域を直線で示した。
見たとおり、図1は1つの連続体の表現であり、積み上げ的イノベーションと非連続的イノベーションを結ぶ線上に、それぞれの範例を表示してある。しかし、何よりもこの図が示唆しているのは、イノベーションという用語が、なぜさまざまの意味に用いられるのか、ということなのだ。
今後2〜3年にわたり、この用語は流行語であり続けるかもしれない。その間は、BPTrendsでも、この連続体線上の各ポイントに相応するアクティビティについて述べた記事を多く取り上げて行きたい。われわれは編集者として、積み上げ的イノベーション、構造的(アーキテクチャル)イノベーション、および非連続的イノベーションの間の明確な判別に努める。しかし読者諸氏も、この区分を念頭にとどめるよう努めていただきたい。そして、イノベーションに関する新しい記事や書籍を読む場合は、この区分に則した分類を自ら試みていただきたい。
イノベーションを巡る誤解
冒頭に紹介したビジネスウィーク誌 2007年6月11日号は、イノベーションの多様な使い方に関する格好のケーススタディをわれわれに提供してくれた。「イノベーションの内側」という特集を組み、その目玉記事として取り上げたのが、「スリーエムにおけるイノベーションの危機:同社のアイデア・カルチャーを瀕死(ひんし)状態に追い込んだシックスシグマ」(※5)と題するカバーストーリーだった。そこでもオライリーとタッシュマンの理論を引用しているが、その本質を正確にスリーエムのケースを巡る議論に適用できていない。
【参考リンク】
※5 COVER STORY: 3M's Innovation Crisis(Business Week Magazine - June 11, 2007)
同記事はまず、スリーエムが2000年にジェームズ・マクナーニ(W. James McNerney)をCEOとして登用したことを指摘する。株価は、1990年代後半の行け行けムードの好況期にもほとんど横ばい、といった低迷状態だった。人員過剰だという意見に異を唱える者は誰もいないと見られていた。マクナーニは全従業員の11%(8000名)を解雇し、その後にシックスシグマを導入した。数千名に及ぶ社員がブラックベルト保持者として育成され、それをはるかに上回る数の社員がグリーンベルト資格取得の訓練を受けた。同社は、DMAIC手法とシックスシグマのための設計(DFSS)の双方を取り入れ、猛烈な勢いでプロセスの改善に取り組み始めたのであった。
マクナーニは就任初年度内に、同社の資本支出を22%──金額にすれば9億8000万ドルから7億6300万ドルにまで削減した。さらに、2003年までに6億7700万ドルまで低減させた。それに伴い、2001年には17%であった営業利益が、2005年には23%に上昇した。対売上高比率でいえば、資本支出は、2001年の6.1%から2003年には3.7%にまで低下した。マクナーニ在任中の利益成長率は、1年当たり22%という勢いであった。
4年半を経て、マクナーニはスリーエムを去り、ボーイング社の新CEOに転じた。スリーエムでマクナーニの後を引き継いだジョージ・バックリー(George W. Buckley)は、現在、シックスシグマを後退させようとしている。ビジネスウィークの記事によれば、イノベーションがなくなったことが、スリーエム社員間の大きな不満になっているという。
スリーエムは、常にイノベーションを推進してきた企業であった。シンサレート※編注やポスト・イットは、同社で発明されたものだ。同社が歴史的に誇示してきたのは、どの時点を取り上げても、総製品売上高の1/3は、それ以前の5年以内に発売した製品から獲得してきたという事実であった。マクナーニが同社を去るまでの5年間について見ると、その売上高比率は25%にまで低下した。現在不満を漏らしている社員たちが示唆するのは、シックスシグマはイノベーションと両立するものではない、ということなのだ。
※編注:シンサレート=米国スリーエムの合成中綿素材のブランド名。マイクロファイバーポリプロピレンとポリエステルファイバーから作られた不織布の一種で、断熱性と吸音性に優れる
この問題について考えるときに念頭に置かなければならないのは、マクナーニが研究開発費を一定に抑えてきたということである。2001年から2005年までの研究開発投資額は、一貫して、年間約10億ドルにとどまった。もし彼が、毎年、研究開発費の増額をいとわなかったとすれば、恐らく新製品による売上高比率を33%に維持したであろう。シックスシグマをやっても、やらなくても、である。
ビジネスウィークの筆者は、この可能性を考慮に入れていない。同誌2007年5月14日号と照合すれば、事態はさらに混乱する。同号が報じた「最もイノベーティブな企業、トップ25社」の記事において、スリーエムは第7位にランキングされているのだ。
マクナーニは、どのようにしてスリーエムを立て直したのだろうか。このことに考えをめぐらせれば、彼が何も新しい考え方を取り入れなかったとは、とてもいえまい。再度、図1を見てみよう。彼が、まさしく、この連続体のとおりにイノベーションを導入したことが、容易に想像できる。
不満を表す社員がいいたいのは、マクナーニが、新技術や新製品を生み出してきたスリーエムのプロセスを変えた(あるいは、それに対する投資を抑制した)ということなのだ。恐らく、そうなのだろう。しかし、そのことで、シックスシグマの非難に向けて長々と記した記事を正当化することは、極めて難しい。
シックスシグマのサークルに関与した経験を、ある程度持つ人であれば、シックスシグマ崇拝者として行動する人種がいることを知っている。彼らは、あらゆる物事をシックスシグマ・ウェイでやるべきだと考える。また、かなりの経験を持つ人であれば、仲間のほとんどは、思慮分別をわきまえた実直な人々であることを知っている。彼らは、シックスシグマが効果を発揮する場もあれば、そうでない場もある、という意見に即座に同意するであろう。
スリーエムはマクナーニのCEO就任を拒否し、株価を1990年代の水準にとどめるべきであった、と主張したい人は誰もいないはずだ。とすれば、われわれが現実に手にしているのは、シックスシグマの驚くべきサクセスストーリーである。そして、恐らくはわれわれに、シックスシグマがうまく機能しない1つの領域を示唆してくれてもいるのだ。
それぞれのイノベーション
これは、まさにオライリーとタッシュマンがHBR 2004年4月号の記事で考察した主題である。優れた企業は組織ユニットを2つのグループに分割する、というのが彼らの解答であった。
1つのユニット・グループは既存ビジネス、もう1つは新規ビジネスを重点とする。別のとらえ方をすれば、1つは全領域での積み上げ的イノベーション、もう1つは絞り込んだ領域での構造的イノベーションあるいは非連続的イノベーションを探求する。そして状況の変化に応じ、それぞれがそれぞれのアプローチを調整するのだ。シックスシグマに携わる賢明な人、さらにいえばCEOの中に、これに異論を唱える人がいるとは、わたしには思えない。
これと少し観点は異なるが、1990年代後期にハマーやそのほかの論者が普及させた図表があった。企業がどのように改善の期間を経由するかを示し、より迅速な改革を求めたものであった。
部門やビジネスユニットにより改革のスピードが異なることは、大企業を例に取れば容易に想像がつく。多くが改善に集中している間に、すでにリデザインに重点を移したところがあるかもしれない。まだリエンジニアリングを中心とする活動に取り組んでいるところもあるだろう。
図2が意味するのは、まさにこのことである。本質的には、オライリーとタッシュマンが、企業に促進を求めた事柄に一致する。今日のビジネスプロセスマネジメント論者のほとんどが提言していることでもある。
リエンジニアリングや非連続的イノベーションの激痛にとらわれたままでいられる企業はない。抜本的な改革も時には必要だが、そのほかの場合には、比較的抑制されたリデザイン活動が求められる。単に目前のプロセス改善に取り組んでいるというのが、ほとんど通常の企業の姿であろう。
図2 ほかよりも早く変化を遂げる部門もある
イノベーションは通常、プロセス改革あるいは製品改革の同義語でしかない。このことに気付き、その可能性を包含する連続体が存在することを納得したとすれば、それらをうまく組み合わせることが次の課題となる。
今後数年間は、誰もが、イノベーションに関するもっと多くの議論を耳にすることになるだろう。重要なのは、関連する事柄の的確なとらえ方、重要な事柄への集中、そして現在の自社で活用できる事柄の見極め、である。
同様に重要なのは、イノベーションという名の下に、無意味な産物が多く出回るであろう、という心構えを持っておくことだ。また、視野の狭い定義や誤った相関関係の提示に引きずり込まれないよう留意しなければならない。ホットな新しいビジネス用語の常として、それらが付きまとって出てくるに違いない。
では、また。
ポール・ハーモン
Original Text
Harmon, Paul, "Innovation and Process Change," Business Process Trends, Email Advisor, Volume 5, Number 11, June 19, 2007.
著者紹介
ポール・ハーモン(Paul Harmon)
ビジネスプロセスに関する情報提供を行うBusiness Process Trends(BPTrends)の創立者/エグゼクティブエディター。Enterprise Alignmentの創立者/チーフコンサルタント。
訳者紹介
高木克文(たかぎ かつふみ)
(株)日本能率協会コンサルティング、テクニカル・アドバイザー。日本BPM協会 ナレッジ研究部会メンバー。グローバル・コンサルティング、リーダーシップ開発研修、ベンチマーキング・プロジェクトなどを中心に活動。戦略、組織、リエンジニアリング、学習する組織、ベンチマーキング、コンサルティングビジネスなどに関する著書、訳書、論稿、多数。
- 「ビジネスとITが出合う場所」のために何が必要か?
- BPMプロジェクト成功の鍵[6] - 継続的改善活動
- BPMプロジェクト成功の鍵[5] - 分析・把握・発見
- BPMプロジェクト成功の鍵[4] - 支援獲得と実行組織
- BPMプロジェクト成功の鍵[3] - ROIの検討
- BPMプロジェクト成功の鍵[2] - 推進組織と機会特定
- BPMプロジェクト成功の鍵[1] - コアアプローチ
- ビジネスプロセス改革と3つのイノベーション
- BPMに求められるプロジェクトマネジメント・スキル
- 第3のプロセス - マネジメントプロセスとは何か?
- BPMのビジネスケースづくり − BPMベネフィット・チェックリスト(後編)
- BPMのビジネスケースづくり - BPMベネフィット・チェックリスト(前編)
- プロセスのマネジメントは、誰が担うのか?
- BPMの神秘を解明する
- BPM市場のこれからを読む
- CEOはどう考えるか
- ビジネスプロセスの標準規格
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
アイティメディアからのお知らせ
人気記事ランキング
- なぜ日本のITエンジニアは優遇されない? 「世界給与ランキング」から見えた課題
- 作業効率爆上がりでも不幸になる? 開発者を襲う「AIのパラドックス」とは
- Active Directoryの心臓部を狙うNTDS.dit窃取攻撃の全貌とは?
- 3800超のWordPressサイトを改ざん 大規模マルウェア配布基盤が82カ国で暗躍
- 中国電力、RAGの限界に直面し“電力業務特化型LLM”の構築を開始 国産LLMを基盤に
- 「年齢で落とされる」は6割超 シニアエンジニアが直面する採用の壁と本音
- IPAが10大脅威2026年版を発表 行間から見えた“日本企業の弱点”
- JFEスチールが挑んだ「脱レガシー」 短期メリットなし、2億ステップの重荷をどう乗り越えた
- 富士通、NECの直近決算から探る 2026年国内IT需要の行方
- IT業界の品質保証、どう変わる? “バグがあっても当たり前”からの脱却方法を考察