「COP26」の“前と後”を読み解く――日本企業が知っておきたい気候変動の潮流:「COP」を通じて考える日本企業の脱炭素戦略(前編)(1/5 ページ)
気候変動に対する世界的な危機感の高まりから、その開催に大きな注目が集まった「COP26」。では今回の「COP26」、そしてそれ以前から続く世界の気候変動に関する大きな流れについて、日本企業は何に注視し、どのように事業戦略に落とし込んでいけばよいのだろうか。「COP」の概要や他国の取り組みをもとに、そのポイントを解説する。
大きな注目が集まった「COP26」
2021年10月31日より11月13日まで英国のグラスゴーにて開催された「COP26」は、パリ協定が採択された「COP21」以来、最大の盛り上がりを見せた。その理由として近年、世界全体で目に見える形で頻繁に大規模な自然災害が発生したため、危機感が強まっていることや、世界最大の温室効果ガス(Greenhouse Gas、以降GHG)排出国であるアメリカが、2021年にパリ協定に復帰したことが背景にある。「COP」と同じくして、SDGsの達成目標期限でもある2030年を一つの節目とし、気候変動に対する世界の本気度がこれまでになく高まっていることが感じ取れる。
言うまでもなく、GHGの削減は政府だけでなく、企業や個人が環境に負荷の掛からない経済活動や生活を能動的に選択し、実践していかないと達成されない。
世界の大きな流れの中で、企業は何に注視し、どのように事業戦略に落とし込んでいけばよいのだろうか。COPの概要や他国の取り組みをもとに、日本企業が今後取り得る戦略構築の一助となるように議論を進めたい。
「COP」とはそもそも何か?
まず、COPの目的や存在意義に関して触れておきたい。COPの発端は20世紀の大量生産、大量消費型経済による環境破壊の反省から、21世紀の持続可能な経済発展の在り方を議論するため、1992年にリオデジャネイロで国際連合が開催した会議にて、世界197カ国によって批准された「気候変動に関する国際連合枠組条約(UN Framework Convention on Climate Change)」がもとになっている。
この条約を実現するための枠組みを締約国の閣僚が議論し、実行案の効果をモニタリングしていくために毎年開催される会議体(the Conference of the Parties)が設置された。その呼称がCOPである。ご存じの方も多いと思うが、COPが理想としているのは、GHGの一つであり、オゾン層を破壊するフロン類の製造・販売を規制したモントリオール議定書(1989年発効)がモデルとされている。同議定書以降、各国政府による規制や企業による代替物質や技術開発が功を奏し、オゾン層を破壊する物質の99%を大気中から無くすことに成功した。この成功体験があったからこそCOPに対する期待値は高く、気候変動対策も成功するという楽観論が世界にあった。
京都議定書(COP3)、パリ協定(COP21)の重要性
しかし、気候変動対策に対して世界全体の合意を得るのは困難を極めた。1995年から通算26回開催されたCOPの中でも、歴史的な合意と呼ばれているのが、京都で開催された「COP3」(1997年)で採択された京都議定書(Kyoto Protocol)と「COP21」(2015年)におけるパリ協定(Paris Agreement)だ。
二つの合意内容の詳細はここでは割愛するが、二つの合意には明確な違いがある。京都議定書は気候変動の責任は37カ国の先進国(「industrialized countries and economies」と表記され中国、インド、ブラジルなどの新興国は除外)にあるとし、法的拘束力のある削減目標が課せされた。一方で、パリ協定で合意された内容は、削減目標を達成する義務はないが、京都議定書以降の目標が定められ、先進国やその他の全ての国家がGHG排出の削減に向けて努力することが約束された。ここまでは多くの方が認識していることだと思料する。
ここで、京都議定書とパリ協定が誕生するまでの間に、18年という長い期間が空いたことに違和感を覚えた読者もいるのではないだろうか。なぜ時間がかかったのか。さまざまな要因はあるが、最大の理由の一つは気候変動の先進国と途上国における責任の所在に関して確執があり、この均衡点を得るまでに18年の歳月がかかったということである。
この問題は、一般的に北半球に多い先進工業国と南半球に集中する途上国との経済や教育などの格差を表す南北問題(North-South Divide)の一つとして取りざたされることが多い。気候変動の文脈では、地球環境が悪化している責任は先進国による経済発展が原因であり、貧困や経済発展に課題を持つ途上国に責任はないため、GHGの削減は先進国が取り組むべきという構図だ。
途上国は1995年にベルリンで開催された「COP1」より、世界全体で気候変動対策を行う重要性は認めつつも、それぞれの国の能力に見合った先進国とは違う責任(「共通だが差異ある責任(Common but Differentiated Responsibilities)」)を求めており、この姿勢は現在でも同じだ(なお、これを拒否し続けたアメリカは2001年に京都議定書から離脱している)。
京都議定書に代わる新しい枠組みが決定されると期待されたコペンハーゲンでの「COP15」(2009年)では、先進国と途上国が責任を押し付けあうのみで期待された合意からほど遠い結果となり、特に気候変動による負の影響を受けやすい大洋州の国々は、COPが機能不全に陥ったと絶望感をあらわにした。
その後2009年以降、北の先進国と南の途上国という南北の対立はCOPでは解決できず、その存在意義すら問われるまでになっていた。そうした世界情勢のなかで、2015年にパリ協定の採択が合意されたことは、悲壮感が漂う世界の雰囲気を一変させたのだった。合意がなされた理由として、中国、インド、ブラジルといった新興国のGHG排出量が既に軽視できないレベルに達していたことが背景にはあるが、少なくともパリ協定によって、南北の国家が「過去の排出」と「現在の排出」の両方に対して、初めて共通の責任を持つに至ったのだ。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
人気記事トップ10
- 非化石証書の上限・下限価格 2027年度から見直しへ
- ペロブスカイト採用の建材一体型太陽光発電システム 札幌市役所で実証
- 注目集まる「次世代革新炉」 日本での社会実装に向けた開発ロードマップが公表
- 揚水発電機の随意契約、需給調整市場における安定的調達とコスト抑制効果の状況
- 蓄電池などの分散型エネルギーリソース、2040年度の導入見通しと課題対応の方向性
- 太陽光発電のケーブルに「追跡タグ」 盗難対策の新たな一手に
- 100kW級の波力発電装置 中部電力らが秋田県能代市で実証
- 蓄電所向けの防音パネル 20dB以上の防音を可能に
- 家庭用蓄電池の並列接続を可能に 産業施設向けの蓄電池導入コストを低減
- 発電側課金の発電事業者から小売事業者への転嫁状況 実態調査の結果が公表
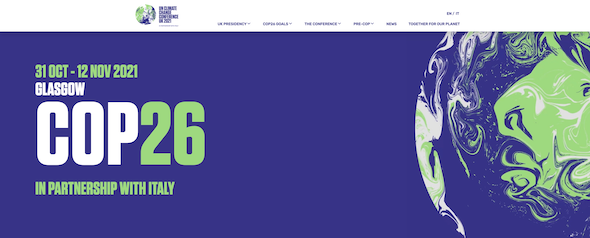 2021年秋に開催された「COP26」の公式Webサイト
2021年秋に開催された「COP26」の公式Webサイト


