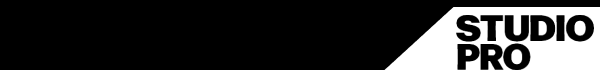「手垢のついたテーマだけど」──生成AI時代のいま「楽園追放」新作で描くこと 水島監督インタビュー:まつもとあつしの「アニメノミライ」(4/4 ページ)
「心のレゾナンス」では何が描かれるのか?
――クリエイティブのお話から、業界の課題までいろいろと伺ってきましたが、最後に本作のテーマについて聞かせてください。
水島:基本的には前作同様、「人を人たらしめているものとは?」という大きなテーマを扱っています。虚淵くんが続編を書ける、と言った突破口も、そこにあるんだと思います。前作で提示したものを、さらに掘り下げていくような形になります。
今、AIに注目が集まっていますが、AI自体を悪く捉えたり、AIが人の仕事を奪うといった視点で、「AIが人とどう違うのか」みたいなところに触れていこうとすると、それは前作と同じ話になってしまうし、AIについてあれこれ言うのは今はやめておいた方がいい、という風潮すらありますよね。短絡的にアンチAIに結び付けてしまう人がいるのは間違いないので。
――そういった先入観や短絡的な捉え方とは対照的に、映画は時間を掛けて集中して、テーマを掘り下げてもらえるのが良い面でもありますよね。
水島:そうですね。まあ、SFでいえば手垢の付きまくったテーマではありますが(笑)。何か新しいかというと実はそうではなくて、めちゃくちゃ普遍的なテーマなんです。10年たってテクノロジーも進化したし、実際AIも進化した。そういう中で「AIと人間、その差はどこにあるのか?」というテーマをど真ん中に据えた「BEATLESS」(原作:長谷敏司)というアニメも作りました。何か、僕がやりたいと言っているわけじゃなくて、そういうテーマの作品が僕のところに来るんだな、と(笑)。延々とこのテーマを扱っている感じがしますね。「機動戦士ガンダム00」のティエリア・アーデもそうでしたし。
――(笑)。
水島:「人間とは何か?」というのは、僕の永遠のテーマというよりは、ずっとついて回るテーマですね。「人間一人一人はそれぞれ個性があって、全く違うものだけれども、何だか『身体』っていう器には入っている」。極端にいうとじゃあ、動物が人の言葉を理解していて、人と同じ言葉を喋ったら、それは動物というよりも人間なんじゃないか? ということと同じなんです。
今、介護ロボットとかいろいろ出てきていますが、AIを搭載してどんどん賢くなり、アルゴリズムによって人に近い反応をするようになってきていますよね。その延長線上に、SF的にはとっくの昔に人と全く同じだけど機械、という存在はいました。「銀河鉄道999」だって、機械の体を手に入れるために999に乗って、機械伯爵が出てくるわけです。
連綿と続くそういった物語の中で、今、僕たちが何を描き出すのか。虚淵くんは、先人とは違う形でそのテーマを掘り下げることができるんじゃないか、という確信があったんだと思います。それが今回のストーリーになっていると、僕は理解しています。
――確かに、AIは手垢のついたテーマでありつつ、これまでSFの世界で描かれてきたような生成AIが実用化されたことで、物語に新たな要素が加わるのではないか、という期待があります。
水島:はい。ただ、それは結局「器」が違うだけで、中身は人間と変わらないわけです。この作品で言うところの「マテリアルボディ」に人工のデータを入れて、人間と同じ振る舞いができたら、それを人間と見分けることはできません。人間がずっと恐れているのは、人間とよく似たものに社会全体を乗っ取られることです。
時代の空気に合わせて物語の方向性を決めるという意味では、世の中がディストピアを描く方向に振れているのであれば、逆にユートピア、つまり機械と人間が共存できる世界をカウンター的に描くという選択肢もあると思います。作り手として、バランスをどう取るのか、ということは常に考えていますね。
ゼロベースで新しいものを作るというのは、よほどの天才じゃない限り難しいでしょう。虚淵くんのようにブレークスルーを見つけられる人が新しい物語を思い付いて、僕らが驚くような何かを提示してくれることを期待しています。
――ディストピアかユートピアか、という観点から見ると、本作はどちらの方向になりますか?
水島:タイトルが楽園追放であるように、「楽園とは何か?」という問いを突き詰めていくと、前作同様「人によって価値観は異なる」という結論に至るでしょう。険しい道であっても、本当に自由でいられるのか? 自分で選択できるのか? あるいは、管理された社会で、安全と生活が保障されている空間で生きていくのか? どちらが幸せか、どちらがあなたにとっての楽園か? という問いは、本作でも重要なテーマです。
ディストピア側は、さらに権力が強まっています。しかし、そこで自分が(社会的に)上の立場になることで、優位な立場を得たいと考える人たちも当然います。そして、実際にそれが可能な世界でもあります。でも、それは今の社会でも、同じことがいえるのではないでしょうか。
――それをディストピアととるか、ユートピアと採るかはまさにそれぞれの価値観なのですが、それらがまさに分断されていて、互いに分かり合えない、というのも現実と地続きの話でもあるように思えます。
水島:現実の世界では、まさにその対立構造を煽っている人たちがいます。そして、その対立構造を作ることで利益を得ている人たちがいるのも事実です。それは、時間の経過も関係しているかもしれません。
――少しポストモダン的な話になりますが、本来は議会制民主主義のように、社会をうまく回すためのシステムがあるはずです。しかし、そのシステムをうまく活用しようとし続けた結果、逆方向にシステムが暴走したり、ほころびてしまっているのかもしれません。
水島:本当の意味での「バランス感覚」を失ってしまった人が多くなってしまったと感じます。そして、それをカリスマ性や権威で抑え込んでいた人たちが亡くなってしまい、崩壊がすごい勢いで始まってしまった。でも、当事者たちはそれに気づいていない。僕たちが描く物語よりも、現実の方が茶番劇のようになってしまっていると感じますね。
――「中の人がそれに気付かない。ある種の身体性というか、現場感覚が喪失してしまっている」というのは、まさに楽園追放で描かれたことでもあり、私たちの現実にも通じるものがあります。だからこそ、この物語には重要な意味があると感じます。
水島:そうですね。描くべきテーマだと思います。自分自身もこういう作品を作るようになるとは想像していませんでしたが、作品自体が時代を映す鏡のようなところがあります。一緒に作品作りをする仲間や友人と話していく中で、自分が持っていなかった視点を手に入れることができたのかもしれません。社会において、どういう立場にいて、何を見て、何を判断しているのか、ということも含めて、作品に生かさないといけないと思っています。「機動戦士ガンダム00」のときにもインタビューで同じようなことを答えましたね。
戦争を描くことを考えたときに、戦争が起こるメカニズムを理解する必要がありました。自分よりもはるかに頭が良くて、世の中を知っている竹田青滋(青は旧字体)さん(毎日放送エグゼクティブプロデューサー)たちと話をする中で、どういうスタンスで自分が戦争と政治を語り、作品に落とし込んでいくのかを考えました。庶民である自分が得られる情報は限られていますが、そこから見て、政治や社会、戦争というものを、自分が学べる範囲で理解しようと努めました。
「戦争の中で若い男女が引き裂かれて...みたいなのは、もう『ガンダムSEED』でやったから、同じことをやってもな」と(笑)。アニメには珍しい報道出身で、現実とフィクションの境界線を予定調和にしない竹田さんに鋼の錬金術師に続き呼ばれたということは、戦争をちゃんと描けということだな、と覚悟を決めて、社会を見る目を更に養おうとしたんです。
楽園追放の話をもらったときも、最初に楽園にあたるサイバーワールドをどう描くか、地上との対比をどうするか、といったことを虚淵くんとよく話していました。最初はもっとサイバーワールド寄りの話になるかな、と思っていたら、すぐに地上に降りていたのでびっくりしました。それは、当時の3DCG制作のリソースの問題に起因していて、野口プロデューサーからキャラクター数の制限などの話が出ていたからでした。そもそも当時は珍しいオールCG制作を目指したチャレンジな企画でしたし、そこまで潤沢な予算感ではなく、OVAブランドの予算で制作していたので、リスクの大きい、大人数やスケールの大きなシチュエーションはできなかったんですね。それで絞り込んでシンプルにした結果が、前作のパッケージでした。今回は劇場版の予算ですし、経験は積めているので、スケールアップしています。
そういう中で描いた社会性というのは、僕自身にもすごくあっていて。
――楽しみですね!
水島:前作から何十年もたっていて、アンジェラが起こした行動がディーバにも地上にも影響を与えている...そんな世界のお話です。先ほど言ったように、テーマは引き継ぎつつ深掘りしていくようなアイデアを虚淵くんが考え出してくれました。そして、活劇としても前作よりスケールアップしたものを描いています。それが今回の作品です。
――うまくまとめて頂いてありがとうございます(笑)。本日は貴重なお話をありがとうございました。26年の公開を心待ちにしています!
©東映アニメーション・ニトロプラス/楽園追放ソサイエティ2
関連記事
 ヒトとアンドロイドの関係を描いたアニメ「BEATLESS」、きょう放送開始
ヒトとアンドロイドの関係を描いたアニメ「BEATLESS」、きょう放送開始
ヒトとアンドロイドの関係を描いたアニメがTBSなどで放送される。 生成AIで一発お手軽に……ではなかったアニメ「ツインズひなひま」 “職人技”が光る制作の舞台裏を聞く
生成AIで一発お手軽に……ではなかったアニメ「ツインズひなひま」 “職人技”が光る制作の舞台裏を聞く
3月に放送されたTVアニメ「ツインズひなひま」は、AIを全面活用した異色の制作手法で話題となった。しかし実態は「AI一発生成」ではなく、モーションキャプチャから3DCGを経てStable Diffusionで変換、手作業レタッチまで含む大規模工程だった。AIが必ずしも省力化につながらない現状と効率化の可能性など、アニメ制作におけるAI活用の実像に迫る。 アニメ「Ave Mujica」制作の舞台裏――監督と制作会社代表に聞く、“圧倒的な内製化”がもたらしたもの
アニメ「Ave Mujica」制作の舞台裏――監督と制作会社代表に聞く、“圧倒的な内製化”がもたらしたもの
ガールズバンドをテーマとしたアニメがここ数年ブームとなっている。2025年3月にエンディングを迎えたTVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」もその1つだが、数あるガールズバンドアニメの中でも、際立った存在感を放っている。本作はどのようにして生まれたのか? IT色の強い制作現場構築の過程など、監督・制作会社代表に詳しく話を聞いた。 「想星のアクエリオン」のすべて キャラデザ決定の舞台裏から特殊な制作手法まで、糸曽監督にインタビュー
「想星のアクエリオン」のすべて キャラデザ決定の舞台裏から特殊な制作手法まで、糸曽監督にインタビュー
約10年の沈黙を破り、待望のアクエリオンシリーズ最新作が1月9日から放送・配信される。最新作「想星のアクエリオン Myth of Emotions」では、従来のイメージを覆すデフォルメキャラが採用され、SNSで大きな話題を呼んでいる。この大胆なチャレンジに込められた意図や、革新的な制作手法、そして作品の魅力について、監督を務める糸曽賢志氏に迫る。 ソニーが「アニメ制作ソフト」をイチから開発する理由――関係者に聞く、課題と解決の先にある“可能性”
ソニーが「アニメ制作ソフト」をイチから開発する理由――関係者に聞く、課題と解決の先にある“可能性”
ソニーグループが2024年5月の経営方針説明会で発表したアニメ制作ソフト「AnimeCanvas」に注目が集まっている。「アニメは世界に通用する」と吉田CEOは述べたが、なぜソニーが手掛けることになったのか、業界をとりまく課題と、その解決策について聞いた。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR