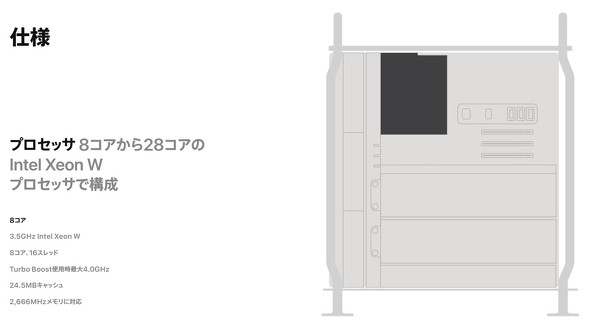巻き返しの準備を進める「Intel」 約束を果たせなかった「Apple」――プロセッサで振り返る2022年:本田雅一のクロスオーバーデジタル(1/3 ページ)
2022年の大みそか――Appleはこの日までに“全ての”MacをApple Silicon化、すなわち自社設計SoC(System-on-a-Chip)への移行を完了するはずだった。しかし現実を見てみると、「Mac mini」の一部モデルと「Mac Pro」の全モデルには“いまだに”Intel製CPUのままである。その理由は定かではないが、Appleが珍しく、自信を持ってアナウンスしていた計画を達成できなかった例となってしまった。
一方でIntelは、パフォーマンスコア(Pコア)と高効率コア(Eコア)のハイブリッド構造を本格採用した「第12世代Coreプロセッサ(開発コード名:Alder Lake)」が好評を持って迎えられ、一時期の“停滞”を脱してかつてのいきおいを取り戻しつつある。
2022年を締めるに当たり、主にAppleとIntelの2社を、SoC(CPU)視点で振り返ってみよう。
優れた正常進化だが驚きには欠けるAppleのSoC
ここ数年、Appleは自社設計のSoCをうまく活用し、さまざまな驚きを演出してきた。
あまりに多くの人が手にしているため軽視されがちだが、iPhone 13/13 Proシリーズが搭載した「A15 Bionicチップ」は、電力効率とピークパフォーマンスのバランスに優れた“名作”ともいえるSoCだった。
それに少し先立ってMac向けに開発された「M1チップ」も、登場してからしばらくはそれを超えるPC向けSoCがなかなか登場しなかったことが、その優秀さを証明している。
下世話な言い方だが、M1チップ搭載の「MacBook Air」を購入した人は、今でもトップクラスのモバイルPC向けSoCが持つ余裕の性能を堪能できていることだろう。現在の視点から見ると、発売のタイミングでM1チップのMacBook Airを購入するという行動を取ったとすれば、明らかに“勝ち組”の行動だと断言できる。
明らかに出来の良さが際立っていたM1チップの登場から2年。さすがに競合他社から性能面で大きく上回る“ライバル”が登場してもおかしくはないと考えていた。しかし、現時点では絶対性能で匹敵するSoC(CPU)はあっても、電力効率面で上回るSoCはいまだに存在しない。
M1チップをパワーアップした「M1 Maxチップ」「M1 Ultraチップ」を搭載して2022年に登場した「Mac Studio」は、コンパクトデスクトップPCと捉えると現在も“無敵”の存在だ。M1チップをリファインした「M2チップ」を搭載するMacBook AirやMacBook Proも、ノートPCとして突出した性能を誇っている。
- →「Mac Studio」「Studio Display」を試して実感した真の価値 小型・高性能に加えてAppleの総合体験も提供
- →新しい「13インチMacBook Pro」は誰のための製品か? 理想的な進化を遂げた「Apple M2チップ」の魅力
- →完成度を極めた新型「MacBook Air」 進化は「M2チップ」だけにあらず
しかし、そんなAppleでも、電力効率よりも「拡張性」や「絶対的な性能」が求められる分野に対する“回答”は出せていない。
M2チップは半導体製造の技術進歩に合わせつつ、毎年のようにiPhone向けにアップデートしているSoCの設計要素を取り込むことで進化を果たした。しかし、そこには驚きをもたらすポイントはない。
Apple Siliconの優位性は「共有メモリアーキテクチャ」や「SoC上の各種プロセッサの協調動作」による部分も大きい。しかし視点を変えると、その優位性はApple Siliconでは拡張性や絶対的性能を確保しづらいというデメリットとなる。
この課題を解決しないことには、Apple Siliconへの“完全な”移行は実現できない。
関連記事
 完成度を極めた新型「MacBook Air」 進化は「M2チップ」だけにあらず
完成度を極めた新型「MacBook Air」 進化は「M2チップ」だけにあらず
7月15日に発売される新しい「MacBook Air」は、Apple M2チップが搭載されることに注目があつまりがちだが、それ以外にも見るべきポイントはたくさんある。発売に先駆けてレビューする機会を得たので、見どころをかいつまんで検証しよう。 「Mac Studio」「Studio Display」を試して実感した真の価値 小型・高性能に加えてAppleの総合体験も提供
「Mac Studio」「Studio Display」を試して実感した真の価値 小型・高性能に加えてAppleの総合体験も提供
「Mac Studio」を使い始めてみると、コンパクトで省電力ながら高いパフォーマンスを発揮できるのはもちろん、別の画期的な点にも気付いた。それは「Studio Display」と組み合わせた場合のAppleが注力している総合的な体験レベルの高さだ。 「M1 Ultra」という唯一無二の超高性能チップをAppleが生み出せた理由
「M1 Ultra」という唯一無二の超高性能チップをAppleが生み出せた理由
M1 Maxで最大と思われていたAppleの独自チップだが、それを2つ連結させた「M1 Ultra」が登場した。半導体設計、OSと開発ツール、エンドユーザー製品の企画開発、その全てを束ねるAppleだからこそ生み出せた唯一無二のチップだ。 「Apple M1」でMacの性能が大きく伸びたワケ Intel脱却計画に課される制約とは?
「Apple M1」でMacの性能が大きく伸びたワケ Intel脱却計画に課される制約とは?
初のMac向けApple Siliconである「M1」がついに発表され、同時にそれを搭載する3つのMacも登場した。M1の注目点を解説しながら、これからのMac移行シナリオについて考える。 「強いIntel」復活なるか 新CEOの2兆円投資がPCユーザーにもたらすもの
「強いIntel」復活なるか 新CEOの2兆円投資がPCユーザーにもたらすもの
Intelのパット・ゲルシンガー新CEOが発表した新しい戦略は「強いIntel」の復活を予感させるかのような内容だった。2兆円を投じた新工場建設をはじめ、新しいIntelの戦略はPCユーザーに何をもたらすのだろうか。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
アクセストップ10
- Lenovoが「Think」ブランドの新製品を一挙発表 「ThinkPad T」シリーズ大幅拡充し、Androidタブレット「ThinkTab X11」も登場 (2026年03月02日)
- レノボの11型Androidタブレット「Lenovo Idea Tab」が3万円で買える (2026年03月02日)
- ついにOCuLink&USB4 Version 2.0(Thunderbolt 5)両対応のeGPUドック「Minisforum DEG2」を試す (2026年03月03日)
- GUI登場以来のUI変更? 「チャット」から「自律実行」へ Windowsを“エージェントOS”に変える「Copilot Tasks」の波紋 (2026年03月03日)
- 「Amazon Echo Show 5(第3世代)」が65%オフの4500円に (2026年03月03日)
- Intel 18AプロセスのEコアオンリーCPU「Xeon 6+(Clear Water Forest)」はどんなCPU? 詳細を解説 (2026年03月02日)
- 配線不要で設置しやすいソーラー充電式防犯カメラ「Anker Eufy SoloCam S340」が25%オフの1万8800円に (2026年03月02日)
- AMDの「Ryzen AI PRO 400」にデスクトップ版登場 50TOPSのNPUがSocket AM5で利用可能 (2026年03月02日)
- エレコム製品が最大26%お得! マウスやキーボードなど買い替えるなら今がチャンス! (2026年03月03日)
- 自宅で本格的なレース体験が楽しめるハンコン「ロジクール G G923d」が31%オフの3万9800円に (2026年03月02日)