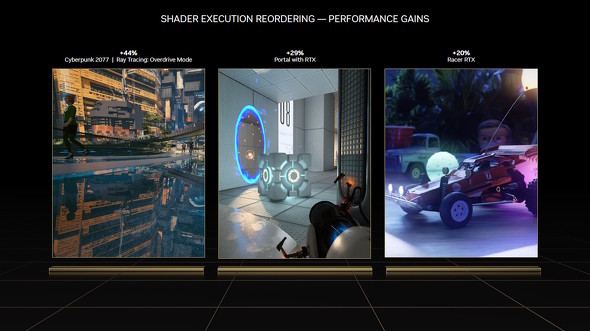GPUの「レイトレーシング処理」改良の歴史をひもとく【GeForce RTX 40シリーズ編】:レイトレーシングが変えるゲームグラフィックス(第6回)(5/5 ページ)
改良ポイント4:Shader Execution Reorderingの搭載
ここまで3つの改良ポイントは、レイのトラバースやインターセクション処理を高効率化するための取り組みだった。4つ目のポイントは、そことは少し異なる観点からの改良だ。
レイトレーシング処理では、ピクセルから放たれたレイがポリゴンなどに衝突して交差判定が確定すると、その箇所に対して「ライティング」や「シェーディング」の演算を行う必要がある。レイが光源に到達した場合は、発射元のピクセルでも同様の処理が行われる。
ライティングやシェーディングに関する演算はRTコアではなく、プログラマブルシェーダーとしての機能を担うCUDAコアで行われる……のだが、問題はレイトレーシング法と、従来的な「ラスタライズ法」では、CUDAコアの使われ方が全く異なるという点にある。
ラスタライズ法では、ポリゴンがラスタライザーによって、一塊の複数ピクセルに分解される。そして、分解された塊たちが“ドバっと”プログラマブルシェーダーに押し込まれる。ラスタライザーによって分解/生成された「一塊の複数ピクセル」は、元々は1枚のポリゴンから誕生したものだから、ほぼ同一の材質のことが多い。
ゆえに、CUDAコアが実行することになるライティングやシェーディングのシェーダープログラムは同一のもので、ほぼ同じテクスチャーを参照することになる。となれば、大増量されたL2キャッシュの利用効率もすこぶるよい。
しかし、レイトレーシング法の場合、隣接する“近しい”ピクセル群から発射されたレイたちも、それぞれの発射角度が異なれば、異なる3Dモデルのポリゴンに衝突する可能性もある。放たれたレイたちが衝突先のポリゴンで“反射”する場合も、それぞれ全く異なる場所にある3Dモデルのポリゴンに当たることも多くなるだろう。
すると、各レイがライティングやシェーディングのためにCUDAコアに外注するシェーダープログラムはバラバラなものになる。当然、L2キャッシュの利用効率も悪くなる。場合によっては、別の仕事で忙しいCUDAコアが受注に応じられない可能性も否定できない。
CUDAコアを含めて、近代GPUのプログラマブルシェーダー類は、SIMD(Single Instruction Multiple Data:1命令で複数データを取り扱うモデル)から発展した実行モデル「SIMT(Single Instruction Multiple Threads:1命令で複数スレッドを取り扱うモデル)」を採用している。ゆえに、一番パフォーマンスを高められるのは「同一のシェーダープログラムを、ひとまとめにされた複数スレッド(ピクセル)に対して実行したとき」となる。この実行モデルは、ラスタライズ法での活用を想定して作られたものなので、どうしてもレイトレーシング法のレンダリングメカニズムとは相性がよくない。
レイトレーシング法でも、プログラマブルシェーダー(NVIDIAならCUDAコア)におけるシェーダープログラムの実行効率を向上できないか――そこでNVIDIAが仕込んだ新しい概念が「Shader Execution Reordering(SER)」だ。
SERは、衝突したとみなされたレイがプログラマブルシェーダーに仕事を発注する際に、「同一のシェーダープログラムで実行できそうな発注」を整理して、可能な限りまとめてから発注する役割を持つ。いわば「交通整理人」のような役割といえる。
これにより、「同じシェーダープログラムが別のCUDAコアで動く」という非効率な状況を抑えることができる。逆にいえば、同じCUDAコアで局所性の高いスレッド(例えば同じ材質の処理)を複数扱えるようになるので、L3キャッシュの利用効率の向上も期待できる。
NVIDIAは、SERについて「レイトレーシングパイプラインに、新しいステージを追加したもの」と説明している。確かにその通りだ。CPUの命令実行モデルの変革と同様に、従来の「逐次実行」のスタイルから、「順不同(Out-of-Order)実行」スタイルにシフトしたともいえる。
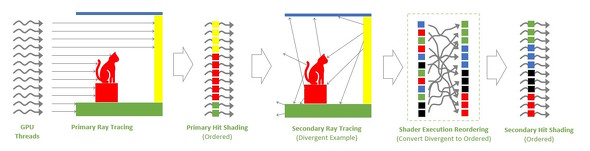 SERの実行イメージ。図の左側は、全てのレイが高い局所性を持って3Dシーン内のポリゴンと衝突したときの“ベストケース”で、衝突したレイに対するライティングとシェーディングの処理は、まとめてプログラマブルシェーダー(CUDAコア)に発注される。図の右側は、全てのレイが方々に反射してしまい、3Dシーン内のポリゴンに対して高いランダム性を持って衝突したときのケースだ。こんな場合でも、SERを使うことで、“近似の”ライティング/シェーディング処理を整理し、まとめてプログラマブルシェーダーに発注できる
SERの実行イメージ。図の左側は、全てのレイが高い局所性を持って3Dシーン内のポリゴンと衝突したときの“ベストケース”で、衝突したレイに対するライティングとシェーディングの処理は、まとめてプログラマブルシェーダー(CUDAコア)に発注される。図の右側は、全てのレイが方々に反射してしまい、3Dシーン内のポリゴンに対して高いランダム性を持って衝突したときのケースだ。こんな場合でも、SERを使うことで、“近似の”ライティング/シェーディング処理を整理し、まとめてプログラマブルシェーダーに発注できるただし、このSERも既存のレイトレーシング対応ゲームで自動活用できる類いのものではない。ゲーム側が制御APIを通じてSERに対応させなければ、SERの恩恵を受けられないのだ。
このことは、当然といえば当然でもある。ゲームのグラフィックスエンジン(グラフィックサブシステム)は、「どの3Dモデルのどのポリゴンには、どんな材質設定がなされていて、どのテクスチャを使うのか」といったことは把握している。ゆえに、衝突が検知された各レイが、これからプログラマブルシェーダーへ発注することになる処理内容にも見当が付く。
どのゲームにも自動対応する(≒アプリとしての特別対応を不要とする)よりも、グラフィックスエンジンで効果的なSERメカニズムを実践する(≒アプリで特別な対応を施してもらう)方が、仕組みを最大限に生かせるのだ。
ちなみに、NVIDIAは開発者向けにGPUパフォーマンスの解析ツール「NSight Graphics」を用意している。SERの利用に当たっては、このツールを使って解析してから実装することが推奨されている。
SERについては、先の改善と同様に現時点ではDirectX Raytracingを介して利用することができない。NVIDIAは他のグラフイックス関連企業と連携して、標準対応に向けた協議を進めているという。
その実際の効果だが、NVIDIA調べで「Cyberpunk 2077」の最上位設定「Overdrive Tracing」においてSERを有効化すると最大44%のパフォーマンス向上効果があるとのことだ。
レイトレを高速化する機能が“てんこ盛り” しかし“個別対応”がネック
このように、GeForce RTX 40シリーズのレイトレーシング機能は、我々が想像していた以上にパワーアップしている。
しかし、ここまでの解説を見てきて「あれ?」と思った人もいるだろう。そう、GeForce RTX 40シリーズならではのレイトレーシング機能を使うには、ゲーム(アプリ)側で個別対応が必要なのだ。
現状では、NVIDIAから提供されているSDKを活用するか、NVIDIAが提供する「Unreal Engine 5」のスペシャルバージョンを使うことで、これらの機能を活用したゲームを開発できる……のだが、開発者にここまでの“特別対応”をするためのリソースがあるかというと、そこまででもないように思える。
PCゲーミング向けGPUの世界では、確かにGeForce RTXシリーズはリーダー的な存在だ。しかし、実際に今回紹介した新機能を“効果的に”実装しているゲームは、NVIDIAが開発協力したタイトル(例えば「Cyberpunk 2077」)以外にほとんど存在しない。
ただし、GeForce RTX 40シリーズに搭載された新機能は、DirectX Raytracingの新バージョンで標準利用できるようになる可能性が高い。AMDのRadeonシリーズでも対応を果たせば、より多くのゲームタイトルで積極的に使われるようになるだろう。
次回は、AMDの「Radeon RX 7000シリーズ」におけるレイトレーシング機能の改善ポイントをチェックしていきたい。
関連記事
 GPUの「レイトレーシング処理」改良の歴史をひもとく【GeForce RTX 30シリーズ編】
GPUの「レイトレーシング処理」改良の歴史をひもとく【GeForce RTX 30シリーズ編】
主にPCゲームで使われるグラフィックス回りについて解説する連載を、約1年ぶりに再開。3回(予定)に分けて、GPUにおけるリアルタイムレイトレーシング(RT)処理がどのように改良されていったのか見ていこうと思う。今回は、NVIDIAの「GeForce RTX 30シリーズ」における改良だ。 2035年、ゲームグラフィックスは「オール・パストレーシング時代」へ――レイトレーシング技術の“先”を見つめる
2035年、ゲームグラフィックスは「オール・パストレーシング時代」へ――レイトレーシング技術の“先”を見つめる
レイトレーシング技術は、ゲームグラフィックスの世界に革命をもたらした……のだが、GPUの性能的にはまだ“完璧”とは言いがたい面もある。いつになったら完璧になるのか――2035年にその瞬間が訪れるという説がある。どういうことなのか、解説していく。 「レイトレーシング」の最大の“敵”とは何か? やっつける方法はあるのか?
「レイトレーシング」の最大の“敵”とは何か? やっつける方法はあるのか?
ゲームグラフィックスにおいて市民権を得つつある「リアルタイムレイトレーシング」。ただ、その活用が進むにつれて、品質面において新しい課題が見受けられるようになってきた。その課題を乗り越える方法はあるのだろうか……? 解説する。 ゲームの中で「レイトレーシング」はどう使われる? 実例を見てみよう
ゲームの中で「レイトレーシング」はどう使われる? 実例を見てみよう
最新ゲーム機が対応したことで注目を集めている「レイトレーシング」という言葉。前回の記事ではその技術的概要を紹介したが、RT(リアルタイムレイトレーシング)の黎明(れいめい)期に登場したデモプログラムや現在のゲームを通して、この記事ではレイトレーシングがゲームのグラフィックスにどのように使われているのかチェックしていく。 最近よく聞く「レイトレーシング」 一体ナニモノ?
最近よく聞く「レイトレーシング」 一体ナニモノ?
エントリークラスの独立(外部)GPUだけでなく最新のゲーム機にも広がってきた「リアルタイムレイトレーシング(RT)」への対応。リアルタイムはともかく、「レイトレーシング」とは一体何なのか? 簡単に解説する。
関連リンク
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
アクセストップ10
- きょう発売の「MacBook Neo」、もうAmazonで割安に (2026年03月11日)
- セールで買った日本HPの約990gノートPC「Pavilion Aero 13-bg」が想像以上に良かったので紹介したい (2026年03月11日)
- 10万円切りMacが17年ぶりに復活! 実機を試して分かったAppleが仕掛ける「MacBook Neo」の実力 (2026年03月10日)
- 12機能を凝縮したモニタースタンド型の「Anker 675 USB-C ドッキングステーション」が27%オフの2万3990円に (2026年03月11日)
- 3万円超でも納得の完成度 VIA対応の薄型メカニカルキーボード「AirOne Pro」を試す キータッチと携帯性を妥協したくない人向け (2026年03月12日)
- 「MacBook Neo」を試して分かった10万円切りの衝撃! ただの“安いMac”ではなく絶妙な引き算で生まれた1台 (2026年03月10日)
- エンスージアスト向けCPU「Core Ultra 200S Plus」登場 Eコア増量+メモリアクセス高速化+バイナリ最適化でパフォーマンス向上 (2026年03月11日)
- 新型「MacBook Air」はM5搭載で何が変わった? 同じM5の「14インチMacBook Pro」と比べて分かったこと (2026年03月10日)
- 高音質・良好な装着感・バッテリー交換式――JBLのフラッグシップ「Quantum 950 WIRELESS」は妥協なきヘッドセットか (2026年03月12日)
- 出張や通勤で荷物が増えても安心な「ミレー ビジネスリュック EXP NX 20+」が27%オフの1万3865円に (2026年03月10日)