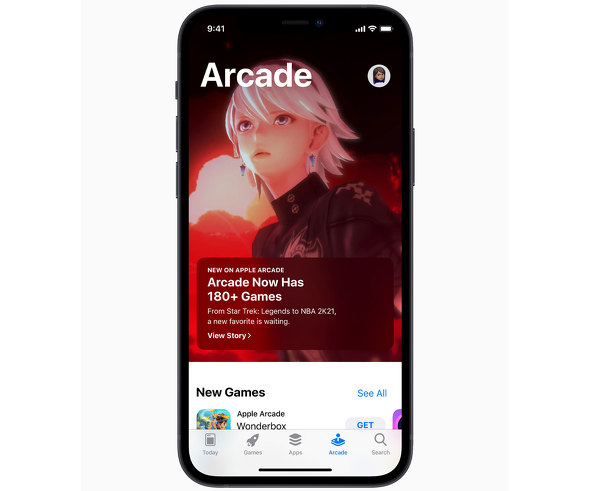Appleはゲーム文化を再興できるか?:Apple Arcadeの挑戦(1/3 ページ)
ゲーム機、パソコン、スマートフォン、タブレット。
21世紀を今生きている人で、これらの機器でゲームをしたことがない人は少数派だろう。中には、ゲームが目的でこういった機器を買った人も少なくないはずだ(ゲーム機は当然そうだろうが)。
最近、電車で真剣な顔をしてスマートフォンをのぞき込んでいる人を見ても、実はゲームをプレイしていた、ということが少なくない。
 Apple Arcadeでプレイできるクラップハンズの新作「CLAP HANZ GOLF」。指1本で実際のゴルフショットを再現した新方式「アナログフリックショット」 の導入で、より直感的かつリアルのゴルフに近いダイレクトなショットを実現している
Apple Arcadeでプレイできるクラップハンズの新作「CLAP HANZ GOLF」。指1本で実際のゴルフショットを再現した新方式「アナログフリックショット」 の導入で、より直感的かつリアルのゴルフに近いダイレクトなショットを実現しているそのゲーム、本当に楽しいですか?
でも、改めて聞きたい。「そのゲーム、本当に面白いですか?」と。
いつの間にか、ゲームはえげつないビジネスの側面を持つようになってしまった。「後ちょっと」というところでアイテムが足りなくなる。数百円の課金をすれば待ちわびていたステージをクリアして次に進め、今日を1日スッキリした気分で過ごせる……。
こうして課金を繰り返し、気が付けば驚くような金額を払っていた、なんていう経験も現代人の多くが通ってきた道だ。
ネット対戦で容赦なく自分を倒していった相手に、このアイテムさえあれば勝てるというアイテムを売りつけられることもある。要はプレイヤーの悔しさをあおってお金をどんどん使わせる仕組みだ。もちろん、お金を注ぎ込めば注ぎ込むほど強くなるので、ゲームの中でも資本主義を痛感させられることがある。なんとも悲しいが、これが昨今のゲーム作りのある種の“定石”となってしまった。
これは2009年、App Storeがアプリ内課金(In-App Purchase)を解禁してから一気に世界に広まった傾向だ。これが原因で何度か社会問題として取り上げられることもあったが、本質は改善しないまま干支(えと)が1周してしまうほどの長い間、我々はこういったものを容認してきてしまった。
もちろん、プレイするか否かも、課金するか否かも本人次第と言えば本人次第でその通りだが、自分や親戚の子供に本当に良かれと思って勧められる人はどれくらいいるのだろう。
当然だが、全てのゲームがこういった作られ方をしているわけではない。中には今日でも、この手の課金が一切ないゲームもある。
ただし、ちょっと進むごとに広告が表示され、しばらくゲームが止まってしまう。まるでCMで引っ張り過ぎて、いつまでも肝心の場面が見られないゴールデンタイムのTV番組のようだ。
ゲーム開発者も、それなりに時間とコストをかけてゲームを作っているのだから、対価を得るのは当然だ。だから、昔はほとんどのゲームがお金を出して買うものだった。しかし、とりあえずプレイさせて中毒にさせて、そこからもうける「アイテム課金」型のゲームは、ゲームを無料で配るのが定石だ。
このようなゲームに負けずに、プレイヤーを増やそうとすると、必然的にゲームそのものは無料で配らないといけない。では、どうやって開発費を回収してもうけるかというと、広告に頼るしかなくなってしまう。
こんなことが20年ほど続く間にもうかるゲームソフト会社は増えたが、文化として語られるゲームは減り、堂々と顔と名前を出してゲームを作るゲームクリエイターの登場も減った印象がある。
こうした状況に一石を投じようとしているのがAppleの「Apple Arcade」だ。
関連記事
 新しい映像体験を得られるジオラマRPGの「ファンタジアン」がApple Arcadeに登場間近!
新しい映像体験を得られるジオラマRPGの「ファンタジアン」がApple Arcadeに登場間近!
Apple Arcade向けの新タイトル「ファンタジアン」がComing Soonコーナーに加わった。開発は、坂口博信氏が率いるミストウォーカーだ。 Apple Arcadeは大きなチャンス――ティム・クックCEOも期待を寄せる大作JRPG「ファンタジアン」が目指すこと
Apple Arcadeは大きなチャンス――ティム・クックCEOも期待を寄せる大作JRPG「ファンタジアン」が目指すこと
坂口博信氏が率いるミストウォーカーがApple Arcade向けに新タイトル「ファンタジアン」を開発している。坂口博信氏や同社に訪れたAppleのティム・クックCEOに話を聞いた。 「Apple Arcade」日本でも9月20日スタート 月額600円(無料トライアルあり)
「Apple Arcade」日本でも9月20日スタート 月額600円(無料トライアルあり)
Appleの有料サブスクリプション式ゲームサービスが、日本でも提供される。月額料金は600円で、新規契約から1カ月間は無料トライアル可能だ。契約は家族6人まで共有できる。 林信行が読み解く Appleが4つのサービスで見せた良質なサービス作りの姿勢
林信行が読み解く Appleが4つのサービスで見せた良質なサービス作りの姿勢
Appleという世界一資金を潤沢にもつ企業が、その資本力を投じることで、もう1度、それぞれのサービスに本来の良さを取り戻そうとする姿勢――これに筆者は“ノブリス・オブリージュ”を感じずにはいられない。 Appleが業界最高水準セキュリティの全貌を明らかに
Appleが業界最高水準セキュリティの全貌を明らかに
Appleが英語の電子ブックレット「Apple Platform Security」を公開した。その意図を林信行氏が読み解く。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
アクセストップ10
- アキバで「DDR4マザー」が売れる理由――MSIから1万円台のB550&Intel H810マザーが登場 (2026年02月28日)
- ASUS JAPANが新型ノートPCを一挙に披露 16型で約1.2kgな「Zenbook SORA 16」など目玉モデルが“めじろ押し” (2026年02月27日)
- 動き出した「次世代Windows」と「タスクバー自由化」のうわさ――開発ビルドから読み解く最新OS事情 (2026年02月26日)
- MSI、Core Ultra 5/7を搭載したCopilot+ PC準拠のミニデスクトップPC (2026年02月27日)
- ソニーの75型4K液晶TV「KJ-75X75WL」がセールで約15万円に (2026年02月26日)
- 幅広いiPadで使えるロジクールのデジタルペン「Crayon(教育現場モデル)」が49%オフの4980円に (2026年02月26日)
- テンキーレスの定番「ロジクール MX KEYS mini」が1.3万円で買える (2026年02月24日)
- デル、Ryzenプロセッサを採用したビジネス向け超小型デスクトップPC (2026年02月26日)
- 攻めの構造と98%レイアウトの賛否はいかに? ロジクールの“コトコト”キーボード「Alto Keys K98M」を試す (2026年02月25日)
- ベンキュー、Mac向けとなる120Hz駆動対応の31.5型4K液晶ディスプレイ (2026年02月27日)