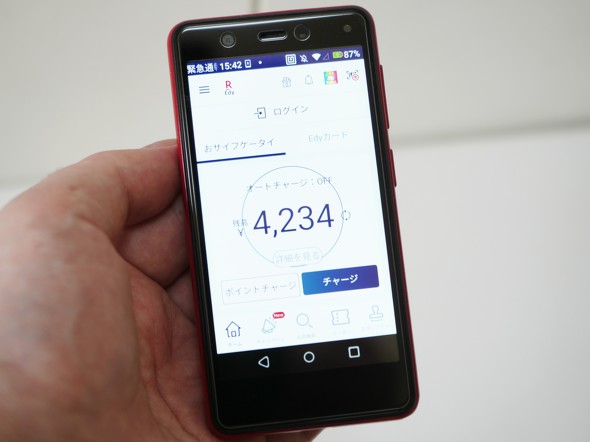「Rakuten Mini」から「Galaxy Z Flip4」に機種変更 大きく変わったユーザー体験と折りたたみならではの欠点も(1/3 ページ)
楽天モバイルが2020年4月、MNOのサービス開始に合わせて、自社ブランド名を冠した小型スマートフォンした「Rakuten Mini」を世に送りだした。ディスプレイが3.6型で、手のひらに収まるほどの小型ボディーに、FeliCaやeSIM搭載というニッチな端末だ。
筆者は発売から数日後にRakuten Miniを入手し、そのサイズ感に驚いたのを鮮明に覚えている。当時、メイン端末にしていたのはドコモの端末だが、サブ回線かつ超小型なサブ端末を探していた筆者にとって、Rakuten Miniの登場は好機逸すべからずで、なんとしても実機を使いたい、と感じた。
それから約3年。長く使い続けていると、当初のワクワク感や満足感は次第に薄れ、そろそろ違う機種は出ないものかと思い始めた。そんなときに飛び込んできた、楽天モバイルによるサムスン電子製の縦折りスマホ「Galaxy Z Flip4」の取り扱い開始、というニュースを目にした筆者はRakuten Miniを手放し、Galaxy Z Flip4への機種変更を決意した。
なぜそうまでして小型スマホから折りたたみスマホへ変えたのか、長年使ったからこそわかった利点と欠点、そしてRakuten Miniでは得られないGalaxy Z Flip4の魅力を語りたい。
Rakuten Miniは小さすぎるゆえの欠点がある
そもそもRakuten Miniがどれくらい小型なのかチェックしていきたい。
サイズは約53.4(幅)×106.2(高さ)×8.6(厚さ)mm、重量は約79g。幅70mm台前半、重量150から200g程度ある一般的なハイエンドスマホと比べると、Rakuten Miniがいかに小さくて軽いかが分かる。
しかし、その分だけ画面サイズは小さく、設定から文字サイズを変更したとしても、大画面スマホよりは表示領域が圧倒的に狭い。そう感じるのは地図やWebなどの閲覧時。楽天Edy残高がそこそこ大きく表示されるなど、かなりストレスに感じた。
そして、最も不便に感じたのがキーボードでの入力。特にテンキーからQWERTY配列のキーボードに切り替えると、個々のキーがテンキーより小さく、指でタッチしづらい。キー1つ分の大きさは身近なものだと米粒1つか2つほどしかなく、ましてやこの小さいキーボードでの早打ちは至難の技だ。10キーに切り替えて入力してみても、押しづらさは変わらなかった。
本体が小さい分、カメラもそれなりのものだ。アウトカメラは有効約1600万画素で、昨今のハイエンドスマホと比べるとかなり劣る。昼間ならほぼ問題ない仕上がりだが、暗所にはかなり弱い。F値は2、ISO感度は最大で6400、手ブレ補正にも対応しない。写真を撮るには物足りないと感じる。
実際にRakuten MiniとGalaxy Z Flip4で撮り比べてみたが、花はRakuten Miniの方がGalaxy Z Flip4よりも実物に近い色味になるが、人物や風景となると、Galaxy Z Flip4の方が格段にきれいな仕上がりとなる。特にRakuten Miniで撮影した人物の写真は輪郭が分かりづらく、顔全体が暗くなってしまう。なお、全てズームイン/アウト、フォーカス合わせをせずにそのまま構えて撮影している。風景もピンボケして、うっすらと建物があるかどうかを認識できる程度だ。
Rakuten Miniを手放す決め手になったのがバッテリー容量だ。バッテリー容量は1250mAhで、連続待受時間は約160時間、連続通話時間は約5.4時間。実使用で約半日以上、バッテリーが持ったことがなかった。バッテリーセーバーを使って極力使うアプリを減らしたとしても、長持ちといえるほどの改善効果が見られなかった。
仮に裏ぶたを開けてバッテリーを交換できたとしても、バッテリーをその都度交換する手間がかかる。そのコンパクトさゆえにバッテリーが長持ちしない、というのはRakuten Mini最大の欠点かもしれない。
過去にユーザーへ告知することなく、対応バンドを変更していたことにも触れておきたい。製造時期によってLTE(FD-LTE/TD-LTE)通信の対応周波数帯(Band)が異なったり、一部ロットで「技適」の不適切表示が判明したりと、好印象を抱けなかった。対応バンドの少なさも、これまで度々指摘されてきた。
- →「Rakuten Mini」の新ロットがLTE Band 1“非対応”に 北米のローミング強化のため
- →「Rakuten Mini」の新ロット、W-CDMA(3G)通信の仕様変更も判明
- →総務省が楽天モバイルに“報告”を要求 「Rakuten Mini」の仕様変更について
- →「Rakuten Mini」の一部ロットで「技適」の不適切表示が判明 ソフトウェア更新で解消へ
他にも、楽天グループの三木谷浩史会長兼社長(参入当時:楽天の会長兼社長)が端末発表時に自慢げに話していた、eSIMオンリーという独特な仕様も、筆者にとってあまり好都合な仕様ではなかった。それは昨今の度重なる通信障害でデュアルSIMがほしい、と感じたからだ。
関連記事
 楽天モバイルの超小型スマホ「Rakuten Mini」に触れる どんな人にオススメ?
楽天モバイルの超小型スマホ「Rakuten Mini」に触れる どんな人にオススメ?
楽天モバイルが、MNOサービス向けのオリジナル端末として「Rakuten Mini」を1月23日に発売した。最大の特徴は、何と言っても超小型のボディー。6型前後のスマホに慣れている筆者がサイズ感や操作性をチェックした。 楽天モバイルが超小型eSIMスマホ「Rakuten Mini」を先行発売 全国6店舗で
楽天モバイルが超小型eSIMスマホ「Rakuten Mini」を先行発売 全国6店舗で
楽天モバイルのオリジナルスマートフォン「Rakuten Mini」が、全国6店舗の楽天モバイルショップで先行販売されている。おサイフケータイが使えるスマホとしては世界最小かつ最軽量(自社調べ)で、eSIM専用端末であることも特徴だ。 総務省が楽天モバイルに行政指導 「Rakuten Mini」の仕様変更について
総務省が楽天モバイルに行政指導 「Rakuten Mini」の仕様変更について
ユーザーに告知のない仕様変更を2度実施した「Rakuten Mini」。その問題に関して、総務省が発売元である楽天モバイルに行政指導を行った。「再発防止策」に関して12月末まで月次の報告も求めている。【追記】 「Galaxy Z Flip4」は先代から何が変わった? Z Flip3 5Gとスペックを比較する
「Galaxy Z Flip4」は先代から何が変わった? Z Flip3 5Gとスペックを比較する
Samsung Electronics(サムスン電子)が発表したフォルダブルスマートフォン「Galaxy Z Flip4 5G」。2021年発売の「Galaxy Z Flip3 5G」の後継という位置付けだ。両モデルの違いについて、比較表を交えながらお伝えしていく。 最新折りたたみスマホ「Galaxy Z Fold4」「Galaxy Z Flip4」の実機に触れて分かった進化点
最新折りたたみスマホ「Galaxy Z Fold4」「Galaxy Z Flip4」の実機に触れて分かった進化点
サムスン電子ジャパンが9月8日、フォルダブルスマートフォン「Galaxy Z Fold4」「Galaxy Z Flip4」を発表した。実機に触る機会を得たので、両モデルの進化を確かめた。同日の国内発表会でサムスン電子ジャパンのCMO 小林謙一氏が、フォルダブルスマホの市場について説明した。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
アクセストップ10
- ガストで人を介さず「テーブル決済」、食い逃げ対策はあるのか? すかいらーくに聞いた安心の仕組み (2026年02月21日)
- 米Orbic、日本市場から事実上の撤退か オービックとの商標訴訟に敗訴、法人登記も抹消 (2026年02月22日)
- ガストの「テーブル決済」をPayPayで試してみた 便利だけど思わぬワナも (2024年04月14日)
- 「Pixel 10a」は何が進化した? 「Pixel 9a」「Pixel 10」とスペックを比較 “aシリーズ初”の機能も (2026年02月19日)
- LTE(4G)にもケータイはあります!! (2026年02月21日)
- ソフトバンクが「iPhone 16e」「Galaxy S25/S25 Ultra」を価格改定 月1円から (2026年02月20日)
- iOSとAndroidで「eSIMクイック転送」がついに解禁 iPhoneとPixelで検証、OSの壁はなぜ越えられた? (2026年02月21日)
- 「ポケモンGO」のバトルシステムを大幅改修 通信環境や端末差による「不整合」を解消へ (2026年02月20日)
- povo2.0の「サブスクトッピング」はどれだけお得? ahamoやLINEMOと比較 安く使うなら“長期”もアリ (2026年02月20日)
- 「Google Pixel 10a」発表 ディスプレイを強化、アウトカメラがフラットに 4色を実機でチェック (2026年02月19日)