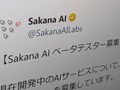生成AI
生成AIにまつわる速報や活用事例、ハウツー、インタビューなど。
Sakana AIが、開発中のAIサービスのテスターを募集している。Google フォームで、2月12日まで応募を受け付ける。
KDDIは、AI開発に特化した新会社「KDDIアイレット」を設立すると発表した。KDDIの中間持株会社であるKDDI Digital Divergence Holdingsと、同社の子会社で、クラウド事業などを手掛けるアイレットを合併する形で、4月1日から始動する。
ソフトバンクは、米OpenAIとの合弁会社SB OAI Japan(東京都港区)から提供する企業向けAI「クリスタル・インテリジェンス」の基盤に、OpenAIの最新プラットフォーム「Frontier」を活用すると発表した。
米Anthropicが、大規模言語モデル「Claude Opus 4.6」用のクレジットを配布している。チャットAI「Claude」上で使えるもので、契約しているプランの利用上限に達した場合に、利用量を50ドル分追加できる。
国連児童基金(ユニセフ)は、子どもの性的ディープフェイクに対する声明を出した。同コンテンツの作成や所持などを、犯罪として規制するよう各国政府に呼び掛けている。
「?よミトく!」のコーナーに活用。AIエージェントがネタ探しから企画提案、企画書作成までを担当しており、企画決定までのプロセスを大幅に短縮できているという。
 Innovative Tech(AI+):
Innovative Tech(AI+):
米Anthropicやカナダのトロント大学などに所属する研究者らは、AIが人間の自律性に与える影響を大規模に調査した研究報告を発表した。
AI要約だけ見て検索を終える人が6割超――NTTドコモのモバイル社会研究所は、このような調査結果を公開した。検索の際にWebサイトのリンクをクリックしない「ゼロクリック検索」の実態を報告している。
安全保障などの観点から国産AIモデルへの関心が高まる中、有力なモデルの一つとして注目を集めるNTTの「tsuzumi 2」。2025年10月、「(国産AI開発競争には)負けられない」という意気込みと共に発表されたtsuzumi 2の滑り出しは。NTTの島田明社長が2025年度第3四半期(25年4月〜12月)の決算会見で「国内の引き合いは2000件ほどある」と現状を明らかにした。
AI音声サービスを手掛ける米ElevenLabsは、5億ドル(780億円、1ドル156円換算、以下同)の資金を調達したと発表した。評価額は110億ドル(1兆7160円)に達し、1年前の3倍以上という。
AIスタートアップの米Timedomainが音楽生成AI「ACE-Step v1.5」を公開した。「RTX 3090」など消費者向けのGPUでも動作し、同様の音楽生成AI「Suno」の前世代モデル「v4.5」を上回る性能とうたう。MITベースの独自ライセンスで、商用利用や配布、複製が可能だが、利用者に対して規約として芸術的誠実性や法令順守を求めている。
ミュージシャンのSKY-HIさんが代表を務める芸能事務所BMSGは、所属アーティストのディープフェイクに対して注意喚起した。
生成AIのヘビーユーザーほど残業時間が長い――パーソルホールディングス傘下のパーソル総合研究所は、生成AIと働き方に関する実態調査の結果を発表した。
アニメ「秘密結社 鷹の爪」の制作元として知られるディー・エル・イーは、米Adobeが一度告知した2Dアニメ制作ソフト「Adobe Animate」の終了を撤回した件に対し、声明を出した。今回の件を「将来的なリスク」と評価している。
 Innovative Tech(AI+):
Innovative Tech(AI+):
ノルウェーのSINTEF、ドイツのマックス・プランク研究所、米イェール大学、米ハーバード大学など世界各国の研究者は、自律型AIエージェントにより、情報操作の手法が根本的に変わろうとしている研究報告を発表した。
Appleは、自律的開発支援「エージェンティックコーディング」を導入した「Xcode 26.3」を発表した。AnthropicのClaude AgentやOpenAIのCodexをネイティブ統合し、AIがプロジェクト構造を把握して設計からテストまでを自律的に実行する。オープン規格MCPにも対応し、開発者が最適なAIモデルを選択できる柔軟な基盤を整えた。
出版業界で働くフリーランスが集う労働組合のユニオン出版ネットワークは、生成AIに関する法規制を求める声明を出した。
合計約12万文字の実際のパブリックコメントのデータに対し、賛否の分類や意見の要約といった分析を行ったところ、10分程度で分析を終えられたという。
ソフトバンクの子会社であるSAIMEMORYは、米Intelと、大容量・広帯域・低消費電力をうたう次世代メモリ技術「ZAM」(Z-Angle Memory)の開発で提携すると発表した。
OpenAIは、コーディングエージェント「Codex」のmacOS向けデスクトップアプリの提供を開始した。複数のAIエージェントをGUI上で並列管理し、複雑な開発タスクを統合制御できる。外部ツール連携やオートメーション機能も備え、既存のモバイル版やIDE拡張機能と設定を共有する。有料プランユーザー向け。
AIだけが書き込みをするSNS「moltbook」がX上で話題になっている。「全てのAIエージェントのためのSNS」と打ち出したSNSで、投稿や投票、共有などのSNSの基本機能は全てAIのみが利用可能。人間は閲覧しか許されていない。
通話中の顧客の怒鳴り声や威圧的な声色をAIによる音声変換技術によりリアルタイムに穏やかなトーンに変換し、オペレーターの心理的負担を軽減する。
米Anthropicの裁判沙汰など、AI開発企業の動向が物議を醸すAI学習目的の海賊版書籍データ収集・利用問題。日本の経済産業省も海賊版被害が拡大傾向にあるとの調査結果を発表しており、国内のクリエイターや企業にとっても無関係な問題ではない。果たして日本の法制度では同様の事態がどう扱われるか、日本弁理士会が1月28日のセミナーで見解を示した。
NASA(アメリカ航空宇宙局)は、1300個以上の異常な天文現象を発見したと発表した。ESA(欧州宇宙機関)の研究者と協力し、ハッブル宇宙望遠鏡のアーカイブ画像をAIで解析した。
中国のAIスタートアップShengShu Technologyは2月2日までに、動画生成AIの新モデル「Vidu Q3」を発表した。APIに加え、Webサービスとしても提供しており、テキストや画像を基に日本語・英語・中国語の音声付き動画を最大16秒まで生成可能。発話者の口の動きを音声と合わせるリップシンク機能も備える。すでに日本のXユーザー間ではアニメーションの出力や日本語読み上げのクオリティーが話題だ。
生成AI利用者の過半数が利用規約を確認していない──LINEヤフーは、生成AIサービスの利用者に対する意識調査の結果を公開した。
米OpenAIが提供するAIチャット「ChatGPT」の日本ユーザー向けの利用料金が1月30日までに、円建てで提供されるようになった。
楽曲のドラマチックな世界観を表現するため「あえて実写ではなく生成AIによる抽象的かつ情緒的な映像表現を選んだ」と説明。
 小林啓倫のエマージング・テクノロジー論考:
小林啓倫のエマージング・テクノロジー論考:
金融や医療などの特定分野(ドメイン)で使う用語・文体・業務手順・評価基準に合わせて開発するAI「ドメイン特化型モデル(DSM)」。その動向を解説する。
イーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業の米SpaceXとAI企業の米xAIが、年内に予定されるSpaceXの新規株式公開(IPO)に先立ち、合併に向けた協議を進めている。事情に詳しい関係者の話と、ロイターが確認した直近の開示情報で判明した。
GMOインターネットグループは、全従業員が業務でのAI活用に取り組む社内向けイベントデー「GMO AI Day」を始めると発表した。「AI前提で仕事をする日」として、毎月第4木曜日に実施する。
スタートアップのマイベストとユビーは1月28日に開催したイベント「AI時代のプロダクトマネジメント反省会 成功も失敗も語るしかNight」で、それぞれが経験した失敗談を紹介し、講演資料も一般公開した。
NTTデータは、デル・テクノロジーズと企業向けのAI活用支援で提携するとの覚書を締結した。2026年半ばをめどに、企業が自社専用の閉じた環境で安全に使えるAIの提供を始める。
情報処理推進機構(IPA)が、2025年に社会的影響が大きかった情報セキュリティの脅威をまとめた「情報セキュリティ10大脅威」の最新版を公開した。個人部門に大きな変化はなかったが、企業などの「組織」部門では「AIの利用を巡るサイバーリスク」が初めてランクインした。
AIエージェントサービス「Genspark」を手掛ける米MainFuncは、Gensparkを日本市場で本格展開すると発表した。日本法人も設立し、拡販に臨む。
米Googleが個人向けのAIサブスクリプション「Google AI Plus」の提供を日本でも開始した。「Gemini」の上位モデルや「Nano Banana Pro」といった生成AIサービスの利用回数を追加する他、200GBのクラウドストレージを提供する。