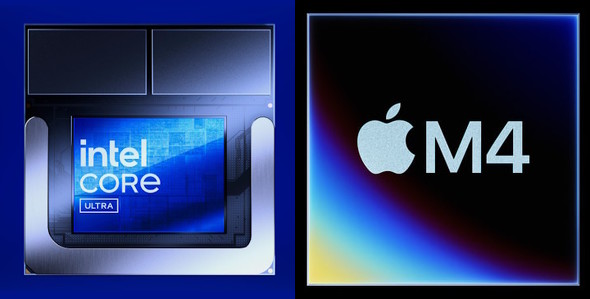大きな転換点を迎えるPCプラットフォーム Core Ultra(シリーズ2)とApple M4チップの「類似性」と決定的な「差異」:本田雅一のクロスオーバーデジタル(1/3 ページ)
PC業界はここ数日、Intelが発表したCore Ultraプロセッサ(シリーズ2)のモバイル向けモデル「Core Ultra 200Vプロセッサ」(開発コード名:Lunar Lake)に関する話題で持ちきりだ。
同社が「Core Ultraプロセッサ」という新ブランドを打ち出してちょうど1年が経過したことになるが、その時よりも、むしろ今回の方が発表内容のインパクトはずっと大きい。
- →新型SoC「Intel Core Ultra 200V」シリーズ発表! AMDやQualcommを上回る性能とバッテリー駆動時間をアピール 搭載PCは9月24日から発売
- →「Core Ultraプロセッサ(シリーズ2)」は驚きの内蔵GPU性能に メモリ帯域が当初発表から“倍増”
以前からアーキテクチャの概要は明らかになっていたCore Ultra 200Vプロセッサだが、そのラインアップが公開されたのは今回が初めてとなる。詳細と全体像を見渡すと、AI(人工知能)時代に向けた同社の野心的な戦略を体現したプラットフォームとなっていることが浮かび上がる。
AIへの対応という観点では、Qualcommの「Snapdragon X Elite」「Snapdragon X Plus」やAMDの「Ryzen AI 300プロセッサ」が先行しているが、これらが新世代のNPU(Neural Processing Unit:推論プロセッサ)のパフォーマンスを前面に出しているのに対して、Intelは高性能NPUの開発だけでなく、技術の“コア”ともいえるCPUアーキテクチャも含めた、システム全体に渡る設計の見直しを図っている。Apple Silicon並みの高効率と、WindowsノートPC向けとしては最高クラスの性能の両立を実現した格好だ。
Core Ultra 200Vプロセッサの特徴を俯瞰(ふかん)すると、最新のApple Siliconである「Apple M4チップ」と似ている点もある一方で、決定的に違うポイントもある。この記事では、Apple Silicon(特にM4チップ)との「類似点」と「差異」に焦点を当てつつ、Core Ultra 200Vプロセッサのプラットフォームとしての可能性と、今後のPCの進化の可能性を考えていきたい。
変化した「最適化ターゲット」に合わせて技術を再構築
Core Ultra 200Vプロセッサの技術全体を見てみると、システムアーキテクチャを設計する際に、ターゲットとするシステムを変えたことを強く感じる。
IntelのCPUは、目的ごとにさまざまな製品レンジやブランドが存在している。しかし、昨今の同社は幅広いレンジを1つの(あるいは極めて近い)コアアーキテクチャでカバーする“万能型”設計を取る傾向にある。サーバやHPC(ハイパフォーマンスコンピューティング)向けから一般消費者向けPC、薄型タブレットPCまで、幅広くサポートしているという印象だ。
近年、同社でも「Pコア(パフォーマンスコア)」「Eコア(高効率コア)」という、Armアーキテクチャでいうところの「big.little」のコンセプトが取り入れられ、サーバ/HPC向けとコンシューマー向けローエンド製品を除き、ヘテロジニアスなCPUへと“変貌”していたIntelのCPUだが、その軸足は常にシステムのスケーラビリティーに置かれていた。
2023年にリリースされた「Core Ultraプロセッサ(シリーズ1)」(開発コード名:Meteor Lake)は、統合型プロセッサ(SoC)として「モバイル特化」「NPU搭載」という点にフォーカスした点が目新しかったものの、アーキテクチャ全体で徹底しきれていなかったことは否定できない。
 Core Ultraプロセッサ(シリーズ1)もモバイルに焦点を当て、NPUを統合したCPU……なのだが、アーキテクチャを子細に見ると、あくまでも第12〜13世代Coreプロセッサの延長線上にあり、刷新感は薄かった
Core Ultraプロセッサ(シリーズ1)もモバイルに焦点を当て、NPUを統合したCPU……なのだが、アーキテクチャを子細に見ると、あくまでも第12〜13世代Coreプロセッサの延長線上にあり、刷新感は薄かったしかし、Core Ultra 200Vプロセッサは、モバイルデバイスへの適応性を高めるべく「電力効率の改善」と「AI処理能力の最大化」に主眼を置いている。
電力効率の面では、基本消費電力(PBP)は17Wまたは30Wという設定だが、17W設定のモデルでは最小消費電力を8Wとすることもできる。これにより、メーカーはより小型/薄型のデバイスの開発がしやすくなる。
新しいCPUコア「Lion Cove(Pコア)」「Skymont(Eコア)」(いずれも開発コード名)は、シングルスレッド性能と電力効率の向上に焦点が当てられている。特にPコアはマルチスレッド(SMT/ハイパースレッディング)機能を削るという大胆な決断をしていることからも分かる通り、「既存の技術を改良して新しいものを作る」というより、「既存技術を見直して再構築する」というアプローチを取っている。
新しい「Xe2アーキテクチャ」を採用するGPUコアも、行列演算性能を高める「XMX(Xe Matrix Extension)エンジン」を搭載することで、AI処理のようなグラフィックス描画“以外”における活躍の場を広げている。
CPUコア、GPUコア、そしてNPUそれぞれがAIワークロードに対し、効率的に処理する命令と回路を搭載しているため、AIのピーク処理性能はシステムトータルで最大120TOPSに達する。合計値としての処理能力の高さもあるが、処理の内容や目的に応じて適切なプロセッサを使い分けられるということの意味も大きい。
 内蔵GPUはXe2アーキテクチャとなった。従来の「Xeアーキテクチャ」では独立GPUとして設計されたチップにのみ搭載されていたXMXを新たに搭載することで、GPUを使った推論演算のパフォーマンスを大きく向上した
内蔵GPUはXe2アーキテクチャとなった。従来の「Xeアーキテクチャ」では独立GPUとして設計されたチップにのみ搭載されていたXMXを新たに搭載することで、GPUを使った推論演算のパフォーマンスを大きく向上したIntelによると、Core Ultra 200VプロセッサはSoC全体のパフォーマンスが向上したにも関わらず、Core Ultraプロセッサ(シリーズ1)に対して最大で40%も消費電力を削減したという。おおむね、消費電力当たりの処理能力(いわゆる「ワッパ」)はApple M3ファミリー相当にまで高まっているようだ。
重要かつ負荷の高い処理に対し、専用の命令セットや専用プロセッサを追加しつつ、それぞれの処理回路の汎用(はんよう)性を引き上げて、システム全体の効率を高める――このアプローチは、Apple Siliconの設計方針との類似性が見られる。しかし、ワッパの大幅な改善は、そもそもの設計の見直し(一新)による着実な成果といえるだろう。
一方で、IntelはApple Siliconの“良い部分”はしっかりと取り入れつつも、あくまでも“PC向け”のSoC(CPU)という位置付けで、応用範囲の広さや適応できるシステム形態の柔軟性も確保している。
関連記事
 「Core Ultraプロセッサ(シリーズ2)」は驚きの内蔵GPU性能に メモリ帯域が当初発表から“倍増”
「Core Ultraプロセッサ(シリーズ2)」は驚きの内蔵GPU性能に メモリ帯域が当初発表から“倍増”
IntelがLuna Lakeこと「Core Ultra 200Vプロセッサ」を発表した。Core Ultraプロセッサ(シリーズ2)のモバイル向けモデルという位置付けだが、どのような特徴があるのだろうか。ドイツ・ベルリンで開催された発表会で得られた情報をもとにまとめた。 Microsoftが「新しいAI PC」の要件を発表 40TOPS以上のNPU搭載が“必須”に
Microsoftが「新しいAI PC」の要件を発表 40TOPS以上のNPU搭載が“必須”に
Microsoftが「新しいAI PC」の要件を発表した。処理性能が40TOPS(毎秒40兆回)以上のNPUを内蔵するCPU/SoCの搭載が必須となる他、メモリやストレージの容量や規格にも要件が定められる。 新型「iPad Pro」がM3チップをスキップした理由 現地でM4チップ搭載モデルと「iPad Air」に触れて驚いたこと
新型「iPad Pro」がM3チップをスキップした理由 現地でM4チップ搭載モデルと「iPad Air」に触れて驚いたこと
Appleが、新しいiPad Proを発売した。従来モデルと比較すると、プロクリエイター向けであることを一層強調したスペックとなっているが、そこまで振り切れた背景には、新しいiPad Airの存在があるかもしれない。イギリス・ロンドンで開催されたハンズオンを踏まえて、その辺をひもといて行きたい。 巻き返しの準備を進める「Intel」 約束を果たせなかった「Apple」――プロセッサで振り返る2022年
巻き返しの準備を進める「Intel」 約束を果たせなかった「Apple」――プロセッサで振り返る2022年
残りわずかとなった2022年。PCにとって一番重要なパーツである「CPU(SoC)」に焦点を当てて、この年を振り返ってみようと思う。 「Apple M1」でMacの性能が大きく伸びたワケ Intel脱却計画に課される制約とは?
「Apple M1」でMacの性能が大きく伸びたワケ Intel脱却計画に課される制約とは?
初のMac向けApple Siliconである「M1」がついに発表され、同時にそれを搭載する3つのMacも登場した。M1の注目点を解説しながら、これからのMac移行シナリオについて考える。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
アクセストップ10
- 10万円切りMacが17年ぶりに復活! 実機を試して分かったAppleが仕掛ける「MacBook Neo」の実力 (2026年03月10日)
- 「MacBook Neo」を試して分かった10万円切りの衝撃! ただの“安いMac”ではなく絶妙な引き算で生まれた1台 (2026年03月10日)
- 新型「MacBook Air」はM5搭載で何が変わった? 同じM5の「14インチMacBook Pro」と比べて分かったこと (2026年03月10日)
- リュック1つで展示会セミナーの音響セット構築レポ 現場で得た“2.4GHz帯混信地獄”を生き抜く教訓 (2026年03月11日)
- セールで買った日本HPの約990gノートPC「Pavilion Aero 13-bg」が想像以上に良かったので紹介したい (2026年03月11日)
- 最新Core Ultra X7 358Hの破壊力! 16型OLED搭載で内蔵GPUがディスクリート超え!? Copilot+ PC「Acer Swift 16 AI」レビュー (2026年03月10日)
- 「iPhone 17e」実機レビュー! 9万9800円で256GB&MagSafe対応 ベーシックモデルの魅力と割り切り (2026年03月09日)
- 「GeForce NOW」がサービスをアップデート Apple Vision ProやMeta Questで最大90fpsのゲーミングが可能に (2026年03月11日)
- 出張や通勤で荷物が増えても安心な「ミレー ビジネスリュック EXP NX 20+」が27%オフの1万3865円に (2026年03月10日)
- 自作PCを売却して「Mac Studio」へ ローカルLLMサーバ移行で得られた驚きの“ワッパ”と安心感 (2026年03月09日)